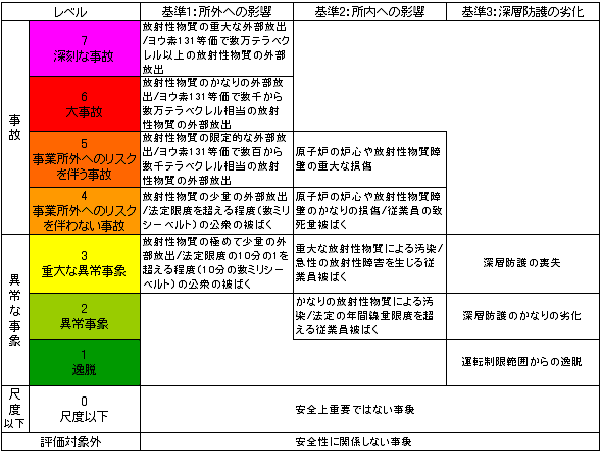|
(2)原子力利用と日本人 ―ゆれ動く原子エネルギーへの期待
●原爆後の日本
原爆が投下された時、私は旧制中学の1年生であった。当時、2年生以上は学徒動員で軍需工場へ働きに出ており、1年生だけが学校に残り、学業・軍事教練と農作業などに従事していた。原爆投下の当日、広島市の中学1年生は、市内中心部の疎開家屋の取り壊し作業に従事していた。そして爆弾の直撃を受けて全滅した。
信じられないことかもしれないが、当時、私たち中学生の話題の中心は、実は原子爆弾の開発をドイツ、日本、アメリカのどこが最初に成功するか?ということであった。
ドイツも日本も殆ど戦争が末期的な状況にきていることは、誰の目にも明らかであった。
しかしドイツ、イタリアはもともと原子物理学の発祥の地であるし、その搬送手段としてのドイツのミサイルV2号はロンドンを連日、脅かしており、ドイツの軍事技術には定評があった。
ドイツと並んで日本も、原子物理では世界的水準にあることは知られていた。我々の毎日の話題は、戦局を一挙に挽回する手段としては、原子爆弾の開発しかないということにあった。
8月6日に広島にたった1発の「特殊爆弾」が投下され、町が全滅したという報道を聞いたとき、我々はそれが「原子爆弾」であることを直ちに察知した。そして日本には、もはや勝ち目がない事が分かった。このときの私たち中学生が第一に感じたことは、原子物理学の理論と技術において日本はアメリカに負けた、という敗北感であった。
そのことが戦後の中学における勉強に、大きな影響を与えた。復員してきた旧海軍士官の物理教師は、原子爆弾の原理を毎回、詳しく解説してくれた。そのためその教師には、直ぐに「原子爆弾」というあだ名がついた。
原子物理への関心は、私の周辺だけではなかった。1949年11月に京都大学の湯川秀樹博士が、日本人として初めて中間子理論でノーベル物理学賞を受賞したとき、日本中の人々は熱狂した。
私は数学・物理系が体質に合っているようであり、当時の物理の成績は年間を通じて95点を越えていた。名古屋大学には湯川秀樹博士に並ぶ原子物理学の権威であった坂田昌一博士が理学部の教授の地位にあり、私は理学部へ入ることを夢に描いていた。
今からでは考えにくいことであるが、当時、エネルギー資源の乏しい日本にとって原子力の平和的利用は、国民に全面的に受け入れられていた。1955年5月13日、東京日比谷公会堂では米国からの使節団を迎えて、「原子力平和利用大講演会」が開催された。聴衆は2,500人で公会堂は超満員になり、場外には1,000人が取り残されるという盛況になった。
同じ年の11月から12月にかけて、東京・日比谷公園の特設会場において「原子力平和利用博覧会」が開催され、36万7千人が入場した。その後、この博覧会は名古屋、大阪など全国20箇所で開催され、これにより原子力政策の民主的基盤ができたといわれる。
1957年8月27日には、茨城県東海村原研の研究用原子炉であるJRR-1が日本で初めて臨界に達した。これについて読売新聞朝刊は1面の4分の3以上の紙面を使って報道し、「太陽の火ともる」−「歴史的快挙」と伝えた。朝日、毎日なども同様にトップニュースとして取り上げた。(中村政雄「原子力と報道」中公新書、18頁)
●70年代から始まった反原発運動
原子力発電に関する反対運動は、1960年代のアメリカから始まったといわれる。(中村「上掲書」26頁)アメリカの戦後の原子力利用は、軍事的には、1948年の潜水艦用原子炉の開発から始まり、1954年には原子力潜水艦「ノーチラス」が完成していた。
世界最初の原子力発電も、アメリカでは出力100kwになるものが1951年に完成した。商業用発電炉が運転を開始したのは、かなり遅れて1963年のことである。この頃から環境保護団体が中心になって、原発に対する反対運動が始まったようである。
アメリカで反原発の運動が本格化するのは、原子力発電所の建設が大幅に増加し、原子力関連企業が巨大化した1960年代後半以降である。
日本ではアメリカより少し遅れて、1970年代初めに原子炉の緊急炉心冷却装置(ECCS)の欠陥が明らかになったころから、反原発運動が激しくなった。
ECCSとは緊急時に原子炉の炉心に水を注入して、「空だき」を防止する装置である。71年5月にアイダホ州の国立原子炉実験所において、ECCSの効果を確かめるため実験を行なったとき、肝心のECCSの水が炉心に入らないという事故が起こった。
日本の科学技術庁は直ちにアメリカへ調査団を派遣し、日本でも原発をかかえる市町村においては大問題になった。その後の調査で、この問題は日本では稼動中の原子炉にほとんど結びつかないことが分かった。(中村「前掲書」28頁)
しかしこのECCS(緊急炉心冷却装置)の問題は各地の原発反対運動に飛び火し、ミネソタ州では原発の放射能が完全に人体に影響しないと分かるまで原発の建設を中止せよという「原子力停止法案」が提出されたが、33対32の1票差で否決された。
72年6月には、カリフォルニア州で5年間原発の建設を中止する住民立法が議会にかけられた。35対65で否決されたものの、その後、「カリフォルニア・クリーン環境法」が州議会で成立し、原発だけでなく火力発電所も海岸には建設できなくなった。
さらに、この原発をめぐる住民投票はヨーロッパに飛び火し、オーストリア、スイス、スウェーデンなどで原発の是非を問う国民投票が行なわれた。
アメリカ、ヨーロッパの原発建設の反対運動は、日本にも大きな影響を齎した。1973年1月27日の朝日新聞夕刊は、四国電力伊方原発(愛媛県伊方町)の建設反対運動を4段で扱った。この頃から、政府の原子炉安全審査に対する不信が高まってきた。
毎日新聞は、73年2月22日の朝刊で「原子炉安全審査に疑問」という記事をトップに据え、5月1日の朝日新聞は、科学部記者の「原子炉、安全か、大丈夫か、安全審査」という解説記事を掲載した。(中村「前掲書」30頁)
ちなみに旧社会党が原発反対の方針を明確にしたのは、1972年からである。社会党では、1月の第35回大会において、原子力に関係のある19県本部の共同提案の形で、「原子力発電所、再処理工場の建設反対運動を推進するための決議」が採択された。
このときまで社会党は、原子力の平和利用としての原発の建設に必ずしも反対してこなかった。しかしここで初めて反原発の立場を明確にし、エネルギー危機は資本主義体制の齎す危機であるとして、イデオロギー的位置づけを明確にした。
●スリーマイル島の原発事故
このような世界的な反原発運動の高まりの中、1979年3月28日、アメリカのペンシルベニア州ハリスバーグにあるスリーマイル島の原子力発電所2号機において、炉心が溶融するという最悪の事故が起こった。
ちなみに原子力発電所の事故については、国際原子力事象評価尺度(INES)により、その深刻さの程度に応じて図表-1に示す8段階の尺度がつけられている。
図表-1 INESの評価尺度の内訳
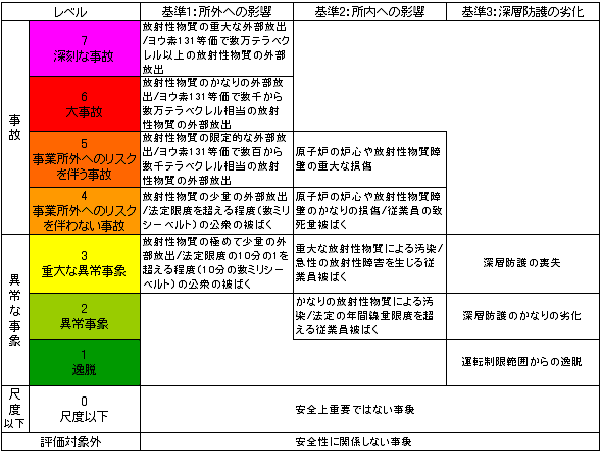
(出典)インターネット「INES」からコピー。
ちなみに、これまで世界的におきた原子力事故で最も深刻なものは、1986年4月に起きたソ連のチェルノブイリ発電所における事故でレベル7(=深刻な事故)、これに対して1979年3月のアメリカ・スリーマイル島の事故はレベル5(=事業所外へのリスクを伴う事故)、1999年9月30日に東海村でおきた日本における最悪のJCO臨界事故はレベル4(=事業所外へのリスクを伴わない事故)である。
スリーマイル島の事故は、1979年3月28日午前4時過ぎに起こった。はじめは2次冷却水のポンプが故障で止まったが、すぐに、原子炉は自動的にスクラム(=緊急時に制御棒を炉心に全部入れ、核反応を停止させる)が機能し、ECCS(緊急炉心冷却装置)が作動して炉心に水の注入が開始された。
しかしそのとき中央制御室の運転員は冷却水が過剰と勘違いして、ECCSを手動で停止させてしまった。その後、1次系の給水ポンプも停止させてしまったため、安全弁から500トンの冷却水が流失して、原子炉は空焚きの状態となり、炉心の上部3分の2が蒸気中にむきだしとなってしまった。
そのため燃料棒が破損し、炉心溶融(メルトダウン)により、燃料の45%、60トンが原子炉圧力容器の底にたまった。周辺住民の被曝は0.01〜1ミリシーベルト程度とされる。
おりしも炉心がとけて地球の反対側の中国まで到達するという映画「チャイナ・シンドローム」が上映されたこともあり、州知事が非常事態を宣言するという事態になった。アメリカ政府はそれ以降、新規の原発の建設中止に追い込まれた。
●チェルノブイリ原発事故
チェルノブイリとは、ロシア語で「苦蓬(にがよもぎ)」を意味している。ヨハネ黙示録には、燃え盛る「にがよもぎ」という大きな星が天から落ちて、川を汚染して多くの人が死ぬという予言がある。そのためキリスト教世界の人々は、チェルノブイリ原発事故の時、まずこのヨハネ黙示録の予言を思い出した。
1986年4月26日、ソ連の古都キーエフに近いウクライナ共和国チェルノブイリ原発4号機で、炉心が溶けて火災が起こる史上最悪の事故が起こった。原子炉の建家は崩壊し、そのために多量の放射性物質が大気中に放出される深刻な事故になった。
その原因は、その夜、無許可で行なわれた発電実験にあった。その実験は原子炉修理の際、いつも無駄にしている熱を利用して、有益な発電ができるかどうかをためすことであった。そのために安全装置を切り、制御棒を殆ど引き抜いたため、出力が急上昇して爆発が起こった。
放射性物質は気流に乗って、世界規模の被爆を齎した。4月27日には海を越えたスウェーデンで放射能が検出され、これにより28日にはソ連政府も事故の公表を余儀なくされた。遠く離れた日本でも、5月3日に雨水から放射能が検出された。
事故翌日の4月27日には、原発に隣接するプリピャチ市の住民4万5000人が避難し、さらに5月3日から6日にかけて周辺30km圏から9万人、結局13万5000人の住民が避難した。周辺住民には急性の放射線障害はなかったといわれるが、その情報はかなり怪しい。
直接の死亡者は作業員・救助隊員の数十名だけであるが、その後の住民のガンや白血病などの疾病を含めると、被災者は数万から数十万にのぼるとされている。
|