
 |
|||||||||
|
|||||||||
| (2)日本の地価と政策 ―日本経済は"花見酒"で亡びた!(その1)
●高度成長が演出した地価高騰 ―笠信太郎の"花見酒"経済論 この所得倍増計画を実現するためには、鉄鋼、石油、自動車、電機など第二次産業の新しい工業立地を実現させる大規模な臨海コンビナートを全国的に形成する必要があった。この用地確保のために、池田内閣の経済審議会・産業立地小委員会は、太平洋ベルト地帯を中心にした新しい工業用地開発のビジョンを全国的に打ち出した。 それは将来、20年にわたる長期の工業立地の展開を視野に入れた壮大な開発計画であった。しかしこの開発計画は、その膨大な用地需要に対する土地政策を持たなかったために、1961年に地価は年間で42.5%という史上最高の上昇率を記録することになった。 日本経済の高度成長政策による地価の高騰は、池田内閣以後も田中内閣の日本列島改造計画や中曽根内閣のバブル的内需拡大政策に受け継がれ、其のたびに地価は狂乱の度を増していった。 笠氏が「"花見酒"の経済」(1962)において懸念したことは、地価が暴騰して、非常に巨額な資金が動くため、一見して経済活動が活性化するようにみえる。しかしそれは、土地取引による経済の活性化は何も生み出さない非生産的なものであり、それによる繁栄、虚構に過ぎないというものであった。笠氏は1967年に亡くなったが、その懸念は40年後の日本経済において現実化してしまったわけである。 笠氏の"花見酒"の出典は落語である。この落語は、明治40年に4代目橘家円蔵が口演した速記録があるそうであるが、後世、林家彦六が得意としたといわれる。その話の筋は、熊さんと辰さんが、向島の花見に酒を売って一儲けしようと考えたことに始まる。 2人は、酒屋の番頭とかけあい三ツ割り(4斗樽の3分の1)を1樽借り出した。柄杓1杯10銭で売り、ついでに花見を楽しもうというまさに一石二鳥の名案を思いついた。そこで客が20銭銀貨を出したときのお釣りとして10銭玉1枚を懐にして、2人は樽をかついで出かけた。 途中、後ろを担いでいた熊さんが、酒の香りに我慢できなくなり、自分が客になって辰さんに10銭払えば、向島まで行かなくても商売になるのではないかと「名案」を思いついた。そして次は、辰さんが客になって熊さんに10銭払って1杯飲んだ。ようやく花見の会場の向島に着いたときには、酒は売り切れて2人はすっかりヘベレケになっていた。道中、さぞ儲かったろうと熊さんが財布をさかさにしたら10銭玉が1枚ころげ出ただけであった。 この話はまことに分かりやすく、そしてばかばかしい。しかし、酒売りの関係者が2人ではなく多数になり、更に花見の場に行く途中で何人かの客に酒を売って儲けていたとすると、この話は俄然、現実味を帯びてくる。 この笠氏の懸念にも拘らず、その後の日本の"花見酒"経済は、高度成長がつづいたため、長い間、破綻しなかった。そのため日本の地価は、値下がりのない安全な、しかも長期的な期待利益が最も高い有利な投資対象と考えられるようになった。 ●戦前・戦後を通じて上昇を続けた日本の地価
図表-4 銀座の戦前の地価推移(円/坪)
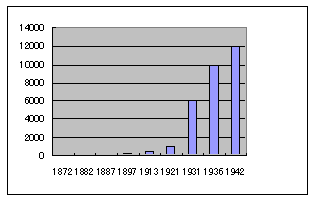
図表-5 銀座の戦後の地価推移(万円/坪)
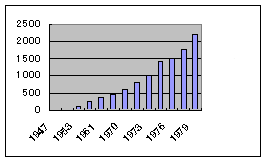 この2つの図表を見ると、戦前・戦後を通じて、日本の代表的商業地である銀座の地価は、ひたすら上昇の一途を辿ってきたことが分かる。 明治5年の5円を当時の米価から計算してみると、この年の米1俵60キロは80銭であり、平成15年の米価は、米1俵13,748円であるから、当時の銀座の地価を現在の米価から換算すると坪当たり86千円という安い地価が導き出される。当時の地価は、米価に比べて安かったわけである。逆にいえば長期的には、米価つまり消費者物価の上昇に比べて、地価の上昇が非常に高かったといえる。 図表-5の銀座の戦後32年間の地価上昇率は年平均14.1%である。驚いたことに、戦前の地価上昇は戦後と殆ど違わない高率なものであり、日本の商業地の地価は戦前・戦後を通じてかなり高率で上がり続けてきたことが想像されるのである。 ●戦後の地価上昇―全国市街地価格指数に見る
図表-6 全国市街地価格指数の変動率の推移
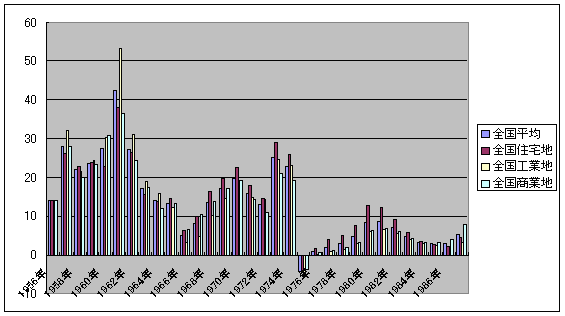 図表-6を見ると、日本の地価変動には大きく3つの山が見られる。 ただでも狭くなった領土の中に、土地も仕事も失った人々は東京、大阪など戦災で廃墟と化した大都会を目指して集まってきた。そのため終戦直後の都市の住宅不足数は420万戸といわれ、敗戦直後から都市を中心とした地価上昇率は、史上最高を記録した。 その上、土地の取引を規制する法規もなく、『不動産業の無法時代』と呼ばれて、闇成金や悪徳業者が住宅地や商業地を買いあさるという状態になった。そこへ財産税が新設されたことにより、旧華族、皇族の跡地が売りに出たことから、1948年以降、土地だけの売買が活況を呈した。 この時代、昨日のアイスキャンデー売りが、今日は不動産屋といわれるほどになった。 ▲神武,岩戸景気の建設投資による地価高騰 これら日本の成長政策の中で、土地政策は大きく遅れていた。日本における国土開発の最初の法律である「国土総合開発法」が1950年に制定されたが、その法律に基づく第一次全国総合開発計画が策定されたのは10年後の1961年のことである。 つまり池田内閣の所得倍増計画の一環として、国土の利用計画というよりは、ハード面を重視した国土計画である第一次全国総合開発計画(第一次全総)が、全国を過密地域と開発地域と分けた拠点開発方式をとって作られた。この開発計画による新産業都市指定をめぐり、1962年には、空前の陳情合戦が展開された。笠氏の心配をよそに、日本列島の土地買いと地価の高騰は、もう誰にも止められなくなっていった。 1956-2003年における10年間ごとの全国市街地価格指数の変動率を計算してみると図表-7のようになる。
図表-7 年代ごとの全国市街地価格の変動率
上の図表を更に見やすくグラフ化したものを図表-8に揚げる。
図表-8 全国市街地の年代別変動
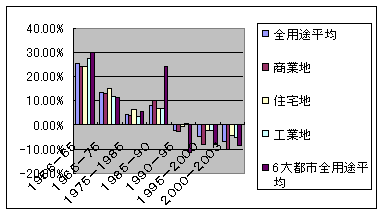 この2つの図表は、日本の地価変動に関する興味深いことを教えてくれる。 企業会計は、簿価で行なわれていたため、日本企業の見せ掛けの資産は小さくとも、資金は銀行が保有土地に対して、時価で融資してくれるので、資金繰りには困らない。また本業の利益が上がらなくても、地価上昇により含み資産が暴騰しているため、株価は下がらない。そして本当に経営に困れば、昔、安く買っておいた土地を少し売却すれば、最終利益は十分確保できる。 この日本資本主義に特有の「土地本位制」が、1960年代に形成され、土地所有者、土地需要者共に日本の地価上昇は崩れないという確信ができてきた。その意味から、笠氏の"花見酒"経済論の懸念は、日本では杞憂に過ぎないと思われるようになっていった。 ▲田中内閣の日本列島改造計画による地価狂乱 大阪万国博覧会で幕開けした日本の1970年代は、最初から波乱を含んだ10年になった。1971年8月15日、ニクソン大統領はアメリカの通貨ドルの金との交換停止を発表して、世界通貨は変動相場制による波乱の時代に入った。このことにより戦後、1ドル360円の固定相場の上に安住してきた日本経済の安定成長にも終止符が打たれた。 実は、日本列島改造計画に先立ち、1967年4月にその前提となる第二次全国総合開発計画(新全総)が作られていた。この計画は、1962年に作られ、「新産業都市」とか「工業整備特別地域」とか、新しい工業地帯を拠点として生み出そうとしたがなかなか進まない第一次全総の大幅な改定を狙ったものであった。 新全総の内容は、丁度、その頃が明治100年になることから、日本の近代化の100年を振り返り、更に、次の1世紀の国土の基本的な枠組みを考えるという壮大な意図を持つ計画であった。 この新全総を下敷きにした田中角栄「日本列島改造論」は、1972年6月に発表された。そしてこの思想を政権の具体的な政策目標とした田中内閣が、その翌月に成立した。田中内閣の成立は、経済企画庁が、戦後の最長の不況という「ニクソン・ショック」を受けた出発であった。そのため、直前の佐藤内閣により作られた72年度予算案は、不況回復のために2兆1千億円を超える公共事業費を組み込んでおり、「これを全額消化すれば地価暴騰間違いなし」といわれるものであった。(中野士郎「田中政権・886日」、312頁) 全国市街地の価格の動きを見ると面白いことが分かる。実は地価は田中内閣の成立するかなり前の1968年から上がり始めており、70年に上昇率はピークとなり、田中内閣が成立した72年には68年の上昇率まで下がっていたのである。田中の不運はいくつかあるが、その最大のものは、1973年秋の第一次石油ショクにぶつかったことであり、しかも其の大事な時期に片腕ともいえる大蔵大臣・愛知揆一に急死されたことにある。 佐藤内閣は、その末期に郵便、医療、交通、電報、その他、家計を直撃する料金の値上げを決めていた。これらの値上げに、石油価格の暴騰による物価上昇が加わり、「狂乱物価」といわれるまでになった。 この石油ショックと列島改造ブームの崩壊により、1975年の日本経済は深刻な不況に突入した。そして戦後、下げることを知らなかった地価が初めて1976年に4.3%の下落を記録した。1975年以降の不況下において、地価の下落は継続するかと思われたが、翌年からは上昇率は低いものの、地価は再び上昇に転じて、日本における「地価神話」の正当性が裏付けられることになった。 |
| Home > どこへ行く、日本1 << 38 39 40 >> | ||